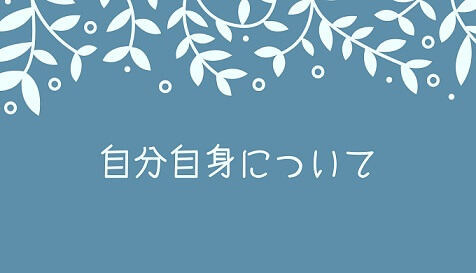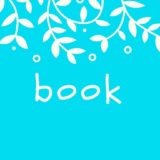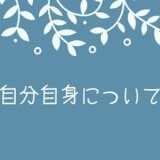【自分自身】あくびが出たら、気づいてほしいこと。
こんにちは!ふくカエルです。
【お伝えしたいこと】
この記事は、あくまでもわたしの個人的な解釈に基づくものです。
中には、「これ違うんじゃないの?」という箇所もあるかと思います。
そのような場合は、温かい目でお見逃しくださいますよう、よろしくお願いします。
もっと、きちんと
くわしく理解したいぞ~~~!
という方には、下記の書籍をご覧いただけるとありがたいです。
あくびは出るもの

今回は、誰もがついついしてしまうあくびについてです。
今まで、あくびなんて深く考えたことがない方がほとんどだと思います。
でもです!
あくびがもたらすものについて、気づいてほしいことがあるのです!はい。
ちょっとでええから、
気づいてほしいことが
あるねん!
気づいてほしいことは、これ!
これです!
あくびが出たときに、気づいてほしいこととは、
あくびとは、身体からのメッセージを伝えるシステムである!
ということです。
実はです。
あくびというものは、眠いから反射的に出るものだけではありません。
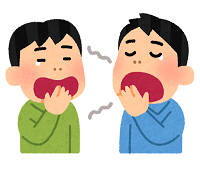
あくびは、身体からいろいろなメッセージを送っています。
 ふくカエル
ふくカエル
 ふくネコ
ふくネコ
あくびをする 1
内臓のすみずみに空気を送り込むこの動きはすなわち、あなたの身体が「気を配ったり議論したりするのは、もうごめんだ」と語っているということなのだ。
アラン「幸福論」より引用
具体的に、どんなメッセージを送っているのかな?
こんなメッセージ!
たとえば、次のようなメッセージを伝えています。
- もう、気を配るのに飽きた
- もう、議論することに飽きた
- もう、考えるのに飽きた
- そんなことより、生きているだけで満足だ
1.もう、気を配るのに飽きた!
まずは、自分の周りにあれこれと気を配るのに飽きたというメッセージです。
あくびをすることで、
ほんまはな、もう、
あれこれと気を使うのが
に嫌になってるねん… ええ加減
ええ加減
うんざりしてるねん。
はよ気づいてな!
という身体からのメッセージを送っているのです。
2.もう、議論するのに飽きた!
次に、他人とあれこれ議論をするのに飽きたというメッセージです。
あくびをすることで、
ほんまはな、
もうあれこれ
議論するのにも飽きてん このことに
このことに
はよ気づいてほしいで!
という身体からのメッセージを送っています。
3.もう、考えることに飽きた!
さらに、あれこれ考えることに飽きたというメッセージです。
あくびをすることで、
ほんまはな、もう、
あれこれ考えることに
飽きてるねん。 もう、こりごりやねん。
もう、こりごりやねん。
という身体からのメッセージを送っています。
4.生きているだけで満足だ!
そしてです。
本当のところ、今この時点での自分自身は、生きてるだけで充分に満足しているというメッセージでもあるのです。
 ふくネコ
ふくネコ
あくびをすることで、
本当のところは、
生きているだけで満足なんや!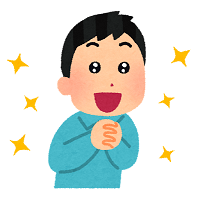 あれこれ苦悩するのに
あれこれ苦悩するのに
飽きて~~~ん!
という身体からのメッセージを送っているのです。
 ふくカエル
ふくカエル
 ふくネコ
ふくネコ
じゃあ、あくびが出たら、実際にどうすればいいのかな?
空気をすみずみまで送り込む
あくび出たら、
まずは、たくさんの空気を吸って、自分の身体の隅々まで空気を行き渡らせて身体の機能を回復させます。
酸素を身体中におくりこんで
あらゆる臓器を
リフレッシュさせるねん。

 ふくカエル
ふくカエル
 ふくネコ
ふくネコ
「疲れた証拠」としてスルーしない
次に、あくびが出たら、
単なる「疲れた証拠」だと早合点して、簡単にスルーしないことです。
 ふくカエル
ふくカエル
 ふくネコ
ふくネコ
耳を澄ませる
あくびを簡単にスルーせずに、自分の身体からの重要なメッセージに耳を澄ませます。
身体からの重要なメッセージ(心の声)に気づきます。
たとえば、
本当のところは
めっちゃウンザリしてるのと
ちゃうか?
とかです。
苦悩することに飽きてる自分自身を認める

さらに、身体からの重要なメッセージに耳を傾けながら、
- 人との関わりあい
- いろいろな駆け引き
などに苦悩することに飽きてしまっている自分自身を認めます。
 「もう、ごめんやねん」
「もう、ごめんやねん」
とウンザリしている
自分自身を認めてあげるねん。
満足している自分に気づく
そして、
一番大事なことは、
あくびが出たら、
実際のところ、
いろいろなことに苦悩せずとも、現時点の自分自身はすでに満ち足りており、生きているだけで充分に満足していることに気づくことです。
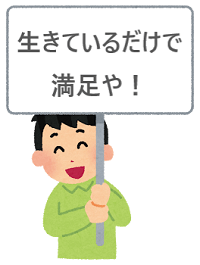
身体からのメッセージに気づくと、どうなるのかな?
しょうもないことに気づく
あくびが教えてくれている身体からのいろいろなメッセージ(とくに、生きているだけで満足であるというメッセージ)に気づくと、
- 他人に気を配ってばかりで、くたびれている自分自身
- 議論の勝ち負けにこだわって、ウンザリしている自分自身
- しょうもないことばかりに苦悩して、へきえきしている自分自身
がとてもしょもないことに気づきます。
平和な証拠であることにも気づく
さらに、あくびが教えてくれている身体からのメッセージに気づくと、
あくびを単なる「疲れた証拠」ではなく、「平和である証拠」としてとらえることができます。
 ふくカエル
ふくカエル
 ふくネコ
ふくネコ
こんな状況で、あくびが出たら、
それこそおかしいよね

「お前さん、ほんまに怖がってるのかい?」となるよね…。
意味あいが変わってくる
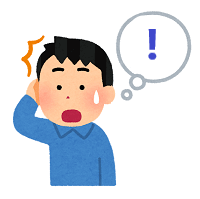
そして、あくびが教えてくれる身体からのメッセージに向き合えると、あくびが持つ意味あいがどんどん変わってきます。
今まであまり価値を見い出せなかったあくびが、
- とても心地よいもの
- 満足度のバロメーター
など、自分にとってプラスの要素を見い出すきっかけとなります。
同じ本をお持ちの方へ
ちなみに・・・・
同じ本(アラン「幸福論」出版社:ディスカヴァー・トゥエンティワン)をお持ちの方へ
「第2章 自分自身について」
「No.048 あくびをする1」
になっています。
お持ちの本とあわせて、ご覧いただけると本当に嬉しいです。
ご自分のお立場で考えてみると、また違った「オリジナルな考え方」を発見できると思うのです。
それはもう、キラキラ光って
こういうことか!
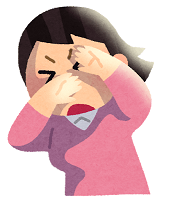 と納得できると思います。
と納得できると思います。
まとめてみたkerokero
- あくびが出たら気づいてほしいこととは、あくびとは身体からのメッセージを伝えるシステムであることです。
- 他人に気を配ったり、議論したり、いろいろなことを考えるのに飽きているメッセージ。そんなことよりも生きているだけで満足しているメッセージなどを伝えています。
- あくびが出たら、まずは深呼吸をして空気を身体のすみずみまで送るようにします。次にあくびを単なる疲れた証拠としてスルーせずに、身体からのメッセージに耳を傾けるようにします。
- 苦悩している自分自身や生きていることに満足している自分自身に気づくことで、あくびのもつ意味あいが変わってきます。
- いままであまり価値の見い出せなかったあくびが、心地のよいもの、満足度のバロメーターとなります。
あくびをすることにはいろいろな意味があります。
- 身体をリフレッシュする
- 飽きていることを実感する
- 生きていることに満足する
ところで、この記事を読んで、
内容がほんまにつまらなくて「あくび」が出た方へ
ほんま、
おもしろくなくて
ごめんね。 このとおり謝る!
このとおり謝る!
ごめん!
ほな、さいなら~~~~。

ふくカエルでした。
なお、アラン先生の引用文は、齋藤慎子さん訳『幸福論』(出版社:ディスカヴァー・トゥエンティワン)によりました。